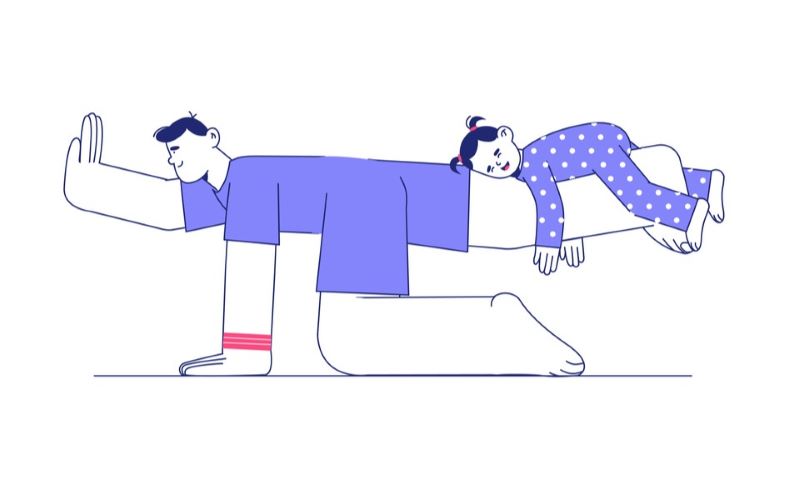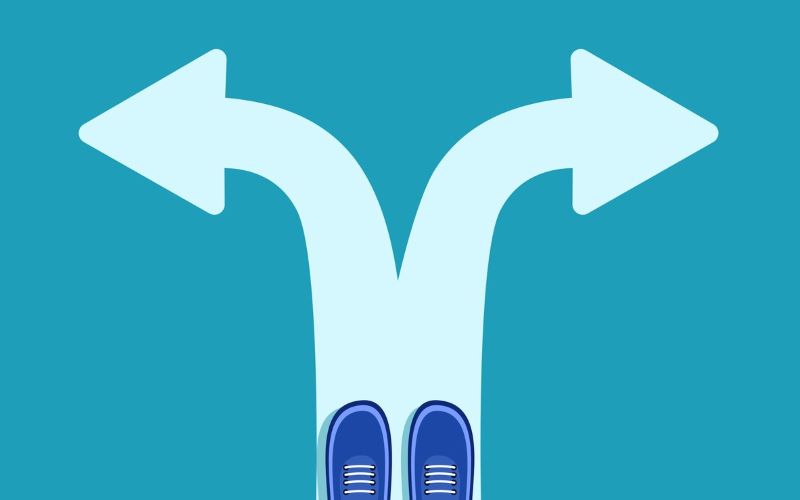「根拠の薄い話が好き」と言ったら、大抵良くない意味に捉えられる。少なくとも、科学の世界では。
リング禍のプロボクシング界を変えるにはどうしたら良いのか? (後編)
今、プロボクシング界に必要なのは、これ以上仮説を積み重ねることではなく、リング禍を減らすための具体的な行動に出ることである。
リング禍のプロボクシング界を変えるにはどうしたら良いのか? (前編)
2025年8月、後楽園ホールで行われたプロボクシング興行で、試合後に意識を失い、のちに亡くなった。同一興行で2名が命を落とすというのは、極めて異例のことで、大きく報じられた。
女子のマラソンランナーでは妊娠出産を経てハイパフォーマンスにつながることもあるが、では、男性アスリートの場合はどうなのだろうか?
仕事が忙しくて、運動不足になりがちな現代。そんな中でも、信じられないくらい運動している人もいる。その理由を、少しサイエンティフィックに考えてみたい。
厚底カーボンシューズから考える「エビデンスを待っていたら遅い」
近年、市民ランニングでも多くのランナーが履くようになった厚底カーボンシューズ。本当に効果があるのだろうか? エビデンスを待っていたら手遅れになる?
生成AIに依存すると脳活動が低下したまま戻らない――脳波測定から導かれたショッキングな観察結果とそれを回避するための方法
生成AIに依存すると脳の活動が停滞し、集中力や意欲の低下を招くことが調査で示唆された。生成AIを使うべきではないのだろうか?
今から1~5年以内に実現されそうなAGI(汎用人工知能)後編 — 差し迫った脅威の割には私達人類の警戒感は乏しい
AI開発の最前線で活躍する研究者らが、「1~5年以内に実現するだろう」と予想するAGI、実現すれば、そのインパクトはどれ程になるのだろうか?
日本の長距離トップランナーを見渡すと、大半が実業団に所属し、競技に専念している。一方で、フルタイムで働きながら、いわゆる余暇時間にトレーニングを重ねるトップランナーもいる。「専業」「兼業」どちらが成功するのだろうか?