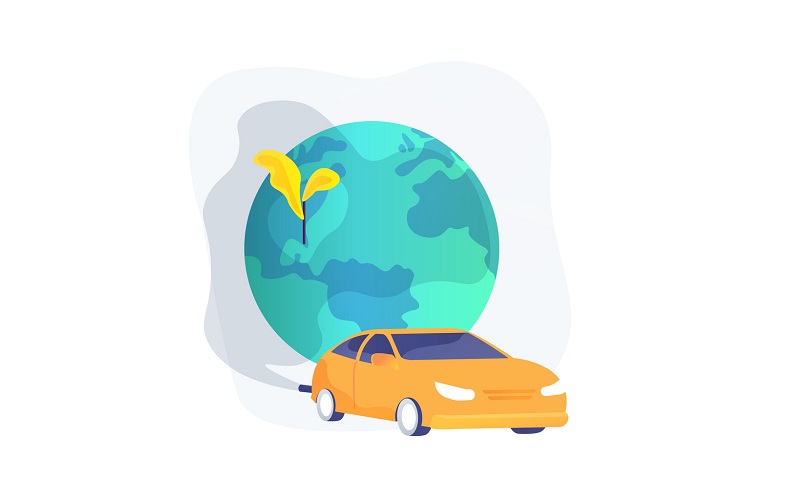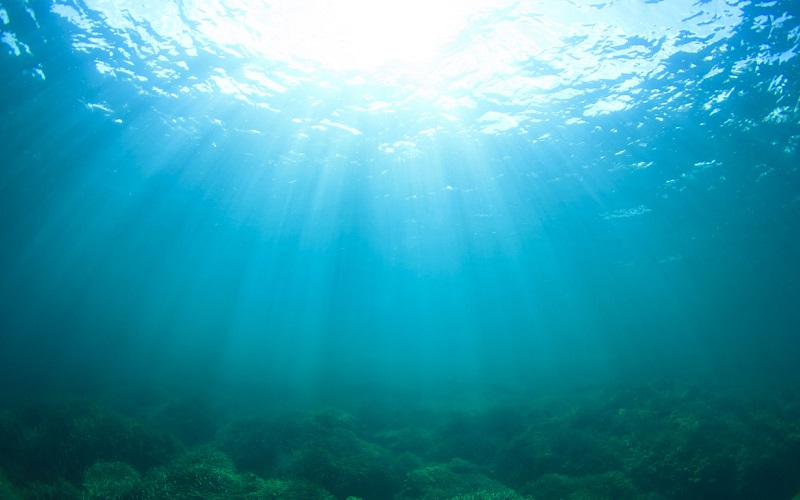AIブームの第2波を巻き起こすGenerative AI:第1回 画像生成AIとは何か
IT業界において、2022年はいわゆる「Generative AI(生成型の人工知能)」が注目を浴びた年だった。 ディープラーニングなど従来のAIは基本的に各種データの「分析」に使われるが、生成型のAIは(同じくディープラーニング技術に基づくとはいえ)文字通り「画像」や「テキスト(文章)」、「コンピュータ・プログラム」など各種コンテンツを「生成」するAIである。この種の人工知能は今後、AIブームの第2波を形成していくことが期待されている。その動向を新たな連載コラムとして紹介していく。初回となる本稿では、まず2022年の夏頃から次々とリリースされた「画像を生成するAI」から見ていくことにしよう。